
基礎生物学研究所

名古屋大学大学院理学研究科

熊本大学発生医学研究所

山梨大学 生命環境学域 高度生殖補助技術センター

長浜バイオ大学・バイオサイエンス学部・エピジェネティック制御学研究室

群馬大学 生体調節研究所

理化学研究所 生命医科学研究センター

東京大学 大学院理学系研究科生物科学専攻
発生細胞動態学研究室

東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医解剖学教室
-227x300.jpg)
放射線影響研究所 分子生物科学部
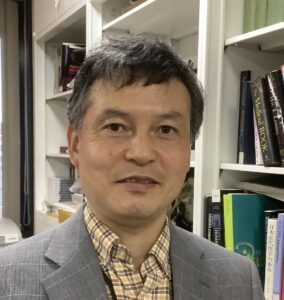
京都大学大学院医学研究科
_石川祐_1-e1714109750162-343x300.png)
横浜市立大学 大学院 医学研究科 臓器再生医学

京都大学医学研究科健康加齢医学・白眉センター

東京大学 定量生命科学研究所 RNA機能研究分野